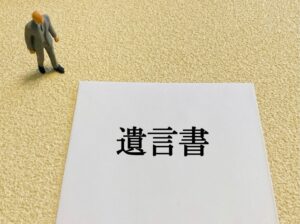法定後見制度と任意後見制度の違いについて教えてください。
成年後見制度には、大きく分けて2つあります。 法定後見制度 判断する力がすでに不十分になったあと、家庭裁判所が後見人を選びます。今すぐ支援が必要なときに使う制度です。 任意後見制度 判断する力があるうちに、将来、もし自 […]
成年後見制度とはどんな制度ですか
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症(にんちしょう)や知的障がい、精神障がいなどで、判断する力が十分でない人を、支えるしくみです。 たとえば、 以上ようなときに、本人の代わりに手続きをしたり、財産を管理した […]
自筆証書遺言の保管制度利用時と公正証書遺言では、遺言書の確認をどのように行えばよいのですか?
自筆証書遺言の保管制度を使うと、遺言書は法務局で保管されます。遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係人は、遺言者の本籍地・最後の住所地などを管轄する法務局に「遺言書情報証明書の交付請求」をすれば、遺言書があるかを確認でき […]
特別縁故者・特別寄与者は、どんな人のことですか?
特別縁故者と特別寄与者は、いずれも被相続人(亡くなった人)の財産に関わる人ですが、以下のような違いがあります。特別縁故者は、相続人がいない場合に登場します。例えば、内縁の妻や長年同居して面倒を見てきた親族・友人など、被相 […]
遺言書に、長男である私を遺言執行者に指定すると書かれていました。私は何をすればいいのですか?
遺言執行者に指定された場合、まず遺言書の内容を確認し、その内容通りに手続きを進める義務があります。主な任務は以下の通りです。
父が死亡して半年後に借金の督促状が届きました。今からでも相続放棄はできますか?
相続放棄ができる可能性はあります。 相続放棄の手続きは、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないのが原則です。しかし、この「知った時」とは、被相続人の死亡を知った時ではなく、自分が相続人 […]
認知症の母を除いて行った遺産分割協議は有効ですか?
無効です。遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があり、その全員が法律行為を有効に行える「意思能力」を持っていることが前提となります。認知症を患っている母は、遺産分割協議の内容を理解し、自身の判断で同意する能力がな […]
暗号資産を保有している場合、遺言書にどう記載すればいいですか?
暗号資産を遺言書で指定する場合、資産の特定が最も重要です。単に「暗号資産」と記載するだけでは不十分です。どの暗号資産を、誰に、どのように譲るのかを具体的に明記する必要があります。記載すべき内容は これらの情報を遺言書に記 […]
亡き父の遺言で、兄が母の介護を条件に財産を譲り受けたのに約束を果たさない時はどうなりますか?
遺言書に「兄に財産を譲る代わりに母の介護をする」といった条件(負担)が記載されている場合、これは「負担付遺贈」という法的な形式にあたります。兄がこの負担を履行しない場合、遺言執行者や他の相続人は、相当の期間を定めて兄に履 […]
全財産を愛人に譲るという遺言は有効ですか?
原則として有効です。遺言は個人の自由な意思に基づいて行われるものなので、誰に財産を譲るかを決めるのは遺言者の権利です。そのため、愛人に全財産を譲るという遺言書も、法律で定められた形式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)に従 […]